記憶を記録してみることの意義
記憶というものが、いかに主観的かは、今日までのいろいろな実例で納得できました。
それなら、その主観的記憶をみれば、「その人」の理解につながるのではないでしょうか。
「その人」を形成しているものは、環境や資質によって形成されたものなので、一人の記憶を検証するということは、一人の人生を理解するだけでなく、時代や社会を知ることにもなるはずです。
そして、時代や社会の中に一人の人生を位置づけることができれば、人間の歴史や社会の本質を見極め、未来の予測にもつながる一助にはなると思います。
しかし、たった一個人の体験には限度があって、個別的な特殊なものではあります。
「事実は小説より奇なり」と言われる所ですよね。
でも、千里の道も一歩より、100の体験談も1個から、ということで、私の記憶を書きとめてみようと思います。
こんなことを思い立ったのは、私の周りで認知症になる友人知人が増えてきたからでもあります。
特に、その中の一人、とても親しい友人は、満州時代に稀有な体験をされた貴重な歴史の生き証人です。
彼女の体験は、私たちが共有するべき希少価値を持っています。
歴史、社会、人生、人間・・・理解し、判断し、選択するときの参考になるものです。
そんなわけで、私が自分の人生を理解するだけでなく、いつか誰かの何かの役にたつかもしれないし、昔の思い出を記録してみます。
主観を前面に出し、思いだすまま順不同になることをお許しくださいね。
さらに、体験した私と、今思い出してる私は同じではないので、もう、小説体です。

両親と妹と私(私以外は故人)
小学一年の思い出
「そういう子はお母さんの子やない。あんたはここまで。うちへは連れて帰りません」
母の声が遠く聞こえた。
枯木の根元で緑の草が揺れていた。
白い点々に見えるのは花だ。
よく見ようと目を落とすと、花の輪郭がにじんで揺れて、次の瞬間、水滴がポトンと落ちて、また、花が大きく揺れた。
こういう時の私は、いつも、自分を失っている。
悲しいとか怖いとかの感情が他人事のようだ。
悲しいのだなと知っているけれど感じない。
でも、涙は出ていた。
空き地のススキは私より高く茂り、白く光る穂先が手招きするように波打っている。
拒絶の言葉は、自動的に懇願を誘いだすはずだ。
それは、一種の化学反応だ。
物質の荷電状態が不安定なところに、化学反応が起きる。
起きて、安定する。
ところが私は、化学反応に負けなかった。
「はい」
子供ながらに覚悟の返事を絞りだした。
素直な良い子教育を受け、できれば良い子になりたかったので、勇気をだして、良い子の行動をとったのだ。
私は動かなかった。
妹をおぶった母も、妹をあやすようなしぐさ以外、動かなかった。
拒否に懇願でこたえるという自然の流れに私が乗れなかったために、事態は膠着状態に陥ってしまった。
泣きわめいて許しを請うという甘えた関係は私たち母子には存在しなかった。
少なくとも、建前上は。
そして、建前の裏にはホンネがあるということを発見するには、このころの私は未熟すぎた。
夕暮れが深くなって、港の灯りがポツリ、ポツリともり始めている。
海に向かって京浜工業地帯を見下ろす丘の上の新興住宅地に私の家はあった。
空き地は丘の一番高い所で、宅地開発を逃れた最後の一画だったが、小学校一年生の私には「地の果て」という言葉で思い描ける唯一の場所だった。
・・・つづく





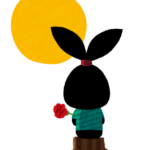




[…] 小学一年の思いで1 より続く […]
[…] 常に気高い理想の姿を追い求めるので、いつだって心の中では「今はダメだけど、いつか良い子に、立派な人に」と歯を食いしばりつつ、実は自信喪失状態で、残念ながら、あまり明るい子供時代ではなかったかもしれません。 […]