小学一年の思い出 2
小学一年の思いで1 より続く
地の果てに、一人残される?

私が自分の生々しい感情を失うのは、多分、その先が想像できない時だ。
お先真っ暗というが、私には真っ白だったので、怖いも悲しいもなかった。
母は無意識のうちに、私の依存心、母がいなければ生きていかれないという危機感にアピールしていたのだと思うが、それは母のかいかぶりだった。
事態を理解できない私に、その罰は無効だった。
豆腐売りのラッパが通り過ぎていった。
空き地の外の日常。
日常の住人として戻る場所のある母と妹。
疎外感というものを自覚した記憶は、これで二度目だ。
最初がいくつの時だったか。
風邪でもひいていたのだろうか、西日の当たる座敷で目を覚ますと、ピッタリ閉じられたふすまの向こうには人の気配もなかった。
家の横の坂道を通る下駄の足音が大きく聞こえて、寝ている私には、頭の上を歩かれているように響いた。
カラン・コロン、ガシガシ、
カラン・コロン、ズズッ、ズズッ
私の上に延びる石ころだらけの道を、下駄履きの足が何本も行ったり来たりしている。
この時、自分がここで死んでいても、こんな風に、みんなは普段の生活を続けているのだ、と気づいてしまった。
ショック、と言うより、呆然自失。
自分が土の下と思ったのは、祖父の葬儀が土葬で、棺に墓地の土をかけた体験があったからだろう。
普段の生活と、この地の果てと、死後の土の下。これが、私が最初に自覚した三界だ。
「おうちには入りません。ご門の下まで入れてください」
「勝手についてきなさい」
私は、ススキの穂のすきまに目を凝らし、ねんねこの紫色を見失わないよう、でも、少し間隔をあけながら小走りについて行った。
私が大学生のころ、母のお茶のみ話に付き合っていた時のことだ。
元気印の母が、ため息混じりに言った。
「よう、あんなことしたなぁ、かわいそやったわ。あんた、オカッパの下から、涙一杯ためた目で、口元に力入れて、私の言葉にうなずいてたわ。」
あの出来事を忘れたわけではない。でも、その時の気持ちはもう忘れていたので、何とも思わなかったが、母の後悔にちょっと「ごめんね」を感じた。
母には叱る理由はあったのに。
母によれば、ついて帰った私は、門の屋根の下まで来ると、中へは入ろうとしなかったそうだ。しばらく外に立っていたらしい。
この意地っ張り母子の窮地を救ったのは父だった。
お父さんの帰る時刻。
これは、会社勤めのお父さんのいる家庭の「理想の家族」始業時刻だった。
「もう分かったら、今日はおうちに入りなさい。」
家路をたどる会社勤めの人が、そろそろ、革靴の音をきしませながら坂道を上りはじめていた。
・・・つづく




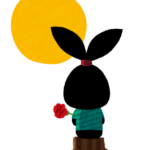





[…] 小学一年の思いで2 のつづき […]
[…] ・・・つづく […]