「このままでは、お子さんは劣等感で性格がゆがむ危険があります。今のうちに何とかしてください。」
私が小学生になって初めての父兄会で、母が受け持ちの先生に言われた言葉です。

期待と不安に緊張しながらも、とても楽しみに出かけた父兄会。
あの頃の母の人生目標は、長女の私を立派に育てることでした。
そして、初めての父兄会は、それまでの成果を確認できる待ちに待ったチャンスだったのです。
立派に。
漠然としたあいまいな人生目標。
具体的なゴールのない目標なので、私がいくら頑張っても、いずれは母を失望させるしかなかったのですが、それがこんなにも早かったとは!
でも、これは、音痴の母子には気づきもしない欠点だったのです。
私が稀有な音痴であることは、小学校の音楽の時間まで証明するチャンスがありませんでした。
先生によれば、音楽の時間に、一人、とんでもなく外れた音程で大声で歌う子がいて、初めはふざけているのかと思ったそうです。
先生の注意もものともせず―自分のことだとは思ってもいませんでしたから―、とても楽しそうに歌っていたので、不思議だったとか。
それが私だと発見されるまでに、時間はかからなかったようです。

音痴改善策
為せば成る、為さねばならぬ、何事も。
これは、母がいつも私に言い聞かせていた言葉です。
やってみなきゃ始まらない!
その言葉通り、母は早速、この状況に「為すべく」動きました。
そして見つけてくれたのが、こともあろうに、児童合唱団でした。
ひばり児童合唱団。
当時は音楽教室やリズム教室といったものはなく、子供が歌の練習をつけてもらえるところといえば、児童合唱団くらいしかありませんでした。
多分、母は、事情を説明したうえで入れてもらったのだと思いますが、まあ、入ってからは大変でした。
児童とはいえ、半プロの合唱団、歌の上手な子供の集まっているところです。
当時隆盛だった童謡歌手と、バックコーラスの集団と言えば一番分かりやすいでしょうか。


今や世界のスターの由紀さおりさんと、そのお姉さんの声楽家、安田祥子さん姉妹をはじめ、本間千代子さんなど、コロンビアレコード専属の童謡歌手が何人も出ている合唱団です。
合唱団自体がコロンビアレコードの専属だったと思います。
小学校の教室でついて行かれない子が、こんなところでどうしてやっていけるでしょうか。
毎日、残されて特訓を受けました。
いくら言ってもなおらない子に、和服姿の先生のピアノの叩き方がだんだん強くなっていったのを思いだします。
皆川和子先生といって、とても歯切れのいい指導上手、ピアノも上手な方でした。
先生の動きの速い、緩急をつけたしなやかな指、ヒラヒラ舞う着物の袖!

「黒猫のタンゴ」という歌を歌っていた皆川おさむ君の叔母さんだと思います。
私が厳しく言われていると、母と一緒に稽古についてきていた妹が、涙を浮かべ歯をくいしばっていたと、後で母から聞きました。
妹は、私より才能に恵まれていたらしく、小学生になって合唱団に入ると、コロンビアレコードの童謡歌手のオーディションを受けるよう勧められたほどです。
でも、母の方針で、何事もお姉ちゃんが先だったので、妹にチャンスはめぐってきませんでした。
妹よ、できの悪い姉が人生の邪魔をしたのですね。
多くの場面で私より優秀だった、今は亡き妹。
ごめんなさい!
おやおや、これを書きながら涙をこらえている私です。
小学校の先生が心配してくれた「劣等感」の危険は、この時が最高だったはずです。
でも、不思議なことに、私は、稽古に通うのが好きでした。
学校の古いオルガンの割れたような響きとちがい、流れるような、時には弾むようなピアノに合わせて歌うのはとても楽しく、みんなのお洒落な雰囲気も好きでした。


今思えば、まだ、自分が見えていなかったのでしょう。
それに、歌の下手な私をからかったり、ましてやイジメたりする人もいなかったのです。
いい環境でした。
始めは洗足まで稽古に通っていましたが、母が友人知人に声をかけ歌を習う子供を集めて、先生に出張教授をお願いしました。
この時、近くの幼稚園を稽古場として借りたのですが、そこには、あのアントニオ猪木さんのご家族が住んでいました。
私は、妹さんのよしこちゃんと仲良しでした。小学校では、席が並んでいたこともあったと思います。
匂いガラスの下敷きがはやっていて、みんな買ってもらっていました。
休み時間には、カラフルな分厚いガラス板の下敷きの角を、ノートにこすりつけて匂いをかぎ合っていたものです。
オレンジガラスは甘いミカンの、グリーンガラスはさわやかなリンゴの匂いをはこんできました。
中学へ通っていたカンジさん(のちのアントニオ)は、私の家の前の坂道をのぼって登校していたのですが、毎朝、私の父と一言二言、軽口をたたきあっていました。
父が「あの子は足も大きいなあ」と言っていたのを思い出します。
私が小学校四年生になった時、猪木さん一家はブラジルに移住することになり、よしこちゃんは、「コーヒーを送るね」と言って気軽に出かけて行きました。

でも実際は、昭和三十年代初期のこと、外国は遠く、ブラジル移住は宇宙へ旅立つような感じでした。
特に、ブラジルは日本の反対側、足元を地球深く掘って、向こう側へ出たところだと聞いて、よしこちゃんの明日は完全に私の想像の外、もう、SFの世界でした。
合唱団の稽古でも、ブラジルへ行く、というのはすごい話題になりました。
輝けるスターで近寄りがたかった安田章子ちゃん(由紀さおりさん)が、休憩時間に、私に近づき、
「お友達がブラジルに行くの?」
と話しかけてくれた時の嬉しさったら!
チェックのギャザースカートで鉄棒にぶら下がっていた私の前に、フワフワのピンクのドレスを着たお人形のような章子ちゃん。
あの場面だけが今も見えるのですが、その前後は霧の中です。
多分私は、まともな返事もできず、「うん」と言ったきりだったのではないでしょうか。



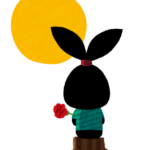






[…] 児童合唱団時代を詳しく書いています→私は音痴だった(1) 私は音痴だった(2) […]
[…] その合唱団には私も入っていたのですが、 […]
[…] その合唱団には私も入っていたのですが、 […]
[…] 私はもともと音痴だし、まったく音楽通ではありません。 […]
[…] その合唱団には私も入っていたのですが、 […]